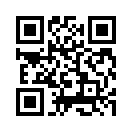生命が存在する可能性もある
太陽系外惑星は、太陽以外の恒星の周りを公転している惑星を指す。今回見つかったのは惑星は直径が地球の約1.4倍で、質量は地球の約4.5倍。8カ月以上にわたる情報収集を経て存在が確認された。岩石を主成分とする地球型の惑星をケプラーが発見したのは初めてで、「ケプラー10b」と命名された。
この大きさの地球型惑星は、ガスでできた惑星に比べて水が存在する確率が高く、恒星からの距離によっては何らかの生命が存在する可能性もある。ただしケプラー10bの場合は恒星との距離があまりに近く、生命の存在には適していないという。
しかしNASAでは、ケプラーによって今後もさらなる発見が期待できることがこれで分かったとしている。
ケプラーは惑星が通過する際にわずかに変化する恒星の明るさをとらえ、大きさなどを測っている。
2011年01月11日 Posted by 木製組み立ておもちゃ at 17:37 │Comments(1)
害がないよう細かい砂とトウモロコシのエキス
設計図
どの種類にも中に設計図が入っています。その絵を見ながら下から順番に、一列に何個のレンガを並べるか、どの種類のレンガを使うか、見ながら誰でも作れるようになっています。参考に作り方の説明をします。
モルタルの作り方木製組み立て模型おもちゃ 車類 ハーレーオートバイ
モルタルは、害がないよう細かい砂とトウモロコシのエキスから作られています。(天然素材のため多少の臭いはします。)付属の容器とヘラを使い、モルタルのパウダーと水を3:1の割合でよく混ぜてください。レンガに付けた時にたれてこない程度の硬さが良いと思います。
モルタルの付け方
各箱の中には、プラスティックか木の台が付いています。その台の上に下から順番にレンガを並べていきます。一番下は側面(横)にモルタルを付けて並べて行ってください。一番下が並べ終わったら、次に、レンガの上にモルタルを付けておいてから二列目を乗せていくと、きれいに、うまく乗せていくことができます。一つ一つレンガにモルタルを付けて乗せていくよりも仕上がりが均等にできると思います。
組み立て方組み立て車類おもちゃ
一列目のレンガの上にモルタルを付けた後、順番に片方の側面にだけモルタルを付け、となりのレンガとくっつくように順番に乗せていきます。横に軽く押してあげると均等にモルタルが側面(横)に付きます。軽く下と横に押してあげると、余分なモルタルがはみ出てきます。はみ出たモルタルはヘラで取ってください。このような方法で下から順番に組み立てていきます。少し乾いたときに歯ブラシ等ではみ出ているところをこすってあげると、よりきれいにできあがります。順番に組み立てていくことで、家やお城が出来上がってきます。子供でも一人で十分作ることができます。作り終わった後も、人形等を使って遊ぶことができます。自分で作りあげた家は、よろこびも倍増でふだんより長く遊ぶことでしょう。
作り変える場合
Teifocの製品は、種類により違いますが、1つから5つのプランを楽しむことができます。その製品が何プラン作れるかは、商品ページの詳細に記載しました。作ったものを作りかえる場合、水に何時間かつけておくことで、バラバラにできます。(モルタルは水に溶けるよう作られています。)水につけ、バラバラになったレンガをすすいで砂を落とし、乾かすことによって、また最初と同じようなバラバラのレンガになります。新しいモルタルで何度も最初から作り変えることが可能です。商品の箱には、何回も作りかえることができるように十分なモルタルのパウダーが入っていますが、別売りでモルタルパウダーだけを購入することもできます。子供だけでなく大人でも十分楽しめる製品になっていますので、是非、親子で作ってくださいね!
2011年01月11日 Posted by 木製組み立ておもちゃ at 17:33 │Comments(0)
ハンマートイやノックアウトボールで鍛えた技術
今回は、ねじったりたたいたりしながら形を変えてゆく、組み立て玩具のお話しましょう。 木製組み立て模型おもちゃ
おもちゃはそれを見ただけで、にぎるもの・転がすもの・たたくもの・動かすものなど、その使い方が誰にでもすぐ分かるものが多いのですが、3歳を過ぎて手先の動きも発達し、構成遊びができる様になってくる頃に使い始めて楽しいのが、組み立て玩具ではないでしょうか。
自分がする何かの行為で形が変わってくる、動かないものが車輪を付けて動くようになる、おもちゃのそんな変化を楽しみ、自分がやったという達成感を感じることができるのかもしれません。組み立て恐竜おもちゃ
2歳児ではねじねじ遊び。単純に入れる側の部品と、受ける側の部品を、相方を替えてねじねじ~~と組み合わせる。本当によく遊びます。
3歳を過ぎると、ハンマートイやノックアウトボールで鍛えた技術で、釘部品を使って、いくつかの部品をつなげだします。 もちろんその時に、恐竜とか車とかをイメージしていれば、おもいきり誉めてあげましょう。
遊び慣れてくると、こんどはボルト・ナット部品を、回す側と受ける側にして、両手を使って締める動作が出来るようになります。こうなるとイメージした形が色々と作れる様になります。 DIYおもちゃ
想像が創造へと発展する。おもちゃ遊びからいつか生活の知恵となる。ひとつのステップに出会うことになるのかもしれません。
2011年01月11日 Posted by 木製組み立ておもちゃ at 17:31 │Comments(1)
いち早く文明開化の風物
プラスチックモデル作りは人気のある遊びのひとつだが、幕末から大正中頃にかけて、和紙で摺られたパーツを切り抜き立体的に組み立てる"立版古"という遊びが流行した。
これは、夏の遊びで、仕上がった作品は、夕涼みの軒先の床机などに豆ランプや蝋燭を点して飾られ、子供に限らず大人もおおいにその出来映えを競い楽しんだ。
"立版古"という呼び名は、上方での俗称で、正式名称は「切組灯籠」「組上げ灯籠」といい、「組上げ」「組上げ絵」ともいわれる。"立版古"という言葉は、江戸時代に錦絵や摺物など木版印刷物のことを、はんこう(版行、板行)と呼んだことに由来するらしい。
"立版古"の起源は、孟蘭盆会の供養の灯籠にある。室町時代頃、御所や大寺院なとでお盆に紙細工の灯籠が飾られたが、これが次第に庶民の間に広まり、江戸時代中期頃に上方で玩具化したといわれる。
"立版古"は一枚摺りの浮世絵版画(錦絵)であり、おもちゃ絵のひとつである。歌麿や写楽が描く鑑賞用の浮世絵とは異なり、双六や物尽くし絵などと同様に消耗される実用むけ版画であるため、かなりの数が出版されたと推測されるにもかかわらず、現存するものは少なく、あまり評価もされてこなかった。 木製組み立てハウスや家具
立版古作者は、絵師としての腕前だけでなく、限られた紙面の中に要領よく各部分を割り付ける科学的な発想力も必要であった。『武江年表』寛政12年の記事に、寛政・享和の頃には北尾政美や葛飾北斎が、文化には歌川国長、豊久が多くの作品を描いたとある。
大阪では、幕末期に中島芳梅と初代長谷川貞信(1848-1940)が活躍し、明治14、5年にかけて長谷川貞信(二世 1809-1879)が活躍した。彼は、約200種ほどの作品を作ったといわれる。その多くは当時の庶民の最高の娯楽であった歌舞伎狂言に題材を取った芝居物であるが、いち早く文明開化の風物も立版古に取り入れた。木製組み立て模型おもちゃ ハウスや家具 ファンタジー別荘
大阪の立版古は明治15年頃が最盛期で、以後いったん新版の発行が途絶えた。明治27年の日清戦争頃に再び新版が発行されたが、木版技術の衰退に伴い、次第に新版の発行は休止していった。以後、大阪では大正になっても遊ばれていたが、子供の遊びの多様化や、出版文化の変化により急速に忘れ去られていった。
大阪の立版古には大判(33cm*24cm)と細版(33cm*15cm)があり、1枚から数枚組で出来るものが多かったが、1組10枚以上の大作ものもかなり発行されていたようだ。錦絵の色が滲まないように注意して和紙で裏打ちし、ハサミや小刀で切り取って、簡単に描かれただけのことが多い完成図を参考にして組立ていく。
2011年01月11日 Posted by 木製組み立ておもちゃ at 17:30 │Comments(0)
箱に今後発売する予定のメカ
昔の組み立て式おもちゃなのですが(トミータカラ関係だと思います)
文字だけで説明するのが難しい商品なのですがお願いします
トミー タカラなどの感じのする組み立て式プラモデル形式のおもちゃ
接着剤不要
価格帯500円ー2500円くらいだった?
善悪というか2つの軍隊が戦争をしている設定
戦車装甲車のような外観 兵士も付属していたような
一方がハイテクぽく一方がローテクぽいギミック組み立て海洋動物おもちゃ
ハイテク 1円玉サイズのプラスティックの円盤をクランクで連続で飛ばす
BB玉を飛ばす ストロー状のミサイルが発射
ローテク 投石器のような物 弓矢のような物
同時期にバンダイは元祖SDガンダム等が人気だったと思われます
ゾイドも発売していたかもしれません
補足
残念ながらダイアクロンではございません:木製組み立て模型おもちゃ 海洋動物 ロブスター:
さらに補足いたしますね
ニットーのオモロイドではないです
ディフォルメというかチョロQ戦車とかチキチキマシン猛レースのメカのデザイン
ハイテク軍(仮称)がいかにも戦車装甲車なデザインに対してローテク軍(仮称)は石器時代中世の兵器
塗装しなくても原材料の色シールで完成するタイプ
箱に今後発売する予定のメカがいくつか載っていた.木製組み立て模型おもちゃ 海洋動物 タツノオトシゴ